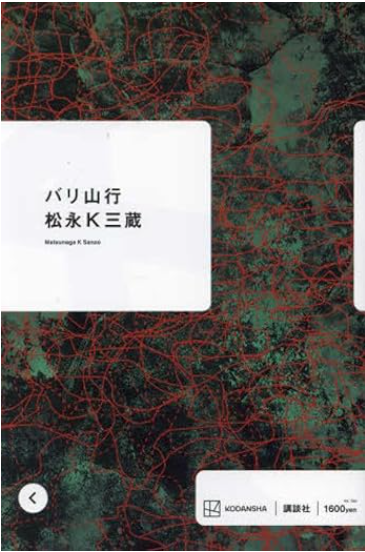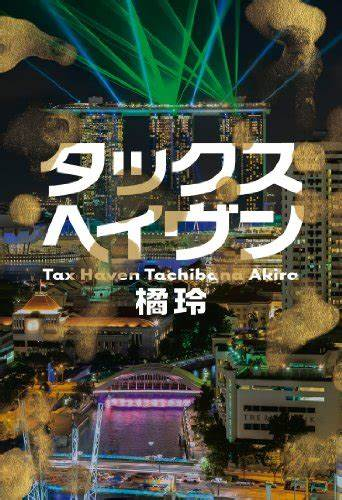世界はなぜ地獄になるのか(橘玲)
タイトル通りですが橘玲さん著”世界はなぜ地獄になるのか”を読んだので簡単に紹介したいと思います。内容に難しい部分もあるのですが、知見が広がり勉強になります。
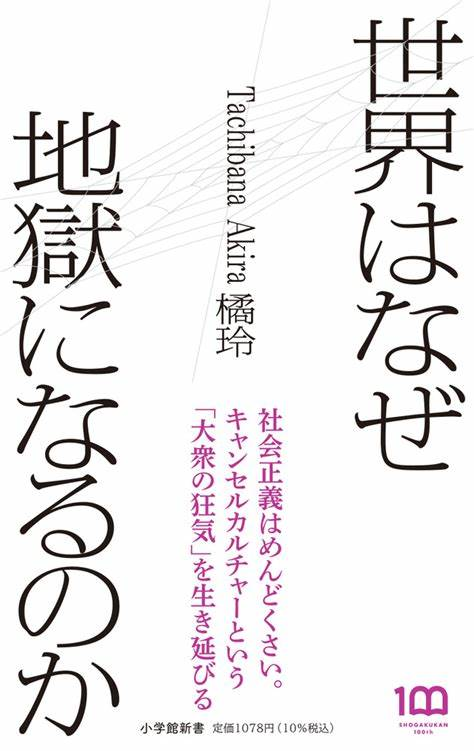
”リベラル”について考えさせられる作品でした。橘玲さんはリベラルを「自分らしく生きたい」という価値観と定義されてました。この定義について、私も違和感は、ありません。保守もリベラルも社会正義を求めているが、対立していく。平等(EQUALITY)と公平(EQUITY)の違い説明など詳しく書かれています。
まず、PART1.小山田圭吾炎上事件です。2021年東京2020オリンピック・パラリンピック(東京五輪)開会式に作曲担当として参加していたミュージシャンの小山田圭吾さんが過去の学校時代のいじめや障害者に対する不適切行為が理由で辞職(キャンセル)に追い込まれた話です。当時、ニュースで聞いたレベルで詳細は把握してませんでしたが、如何に意図的にメディアに貶められたか、事実を曲げ、目を引く部分のみを強調して伝えられ、ソーシャルメディアで炎上したかが語られてます。世代が違うこともありミュージシャン小山田圭吾をよく知らないため、小山田圭吾さんに強く感情移入は出来ませんが、メディア報道の姿勢には怒りを感じます。よくSNSやイーロン・マスクなどがオールドメディアを批判してますが、このような点が、変わらぬオールドメディアの悪しき点だと思います。
PART2.ポリコレと言葉づかいは、ポリコレ=ポリティカル・コレクトネス、政治的な正しさ(適切さ)のお話。いくつか、たとえ話の紹介がありますが、国や人種の違いによる価値観の違いから、起こる勘違いや摩擦の話紹介があり、これから世界に旅行へ行こうとしてる私には刺さる話でした。
話の中に会社での上司や先輩などの敬称の話題がありました。日本は「さん」づけでアメリカは呼び捨て。私が過去に勤めていた会社では入社時は、メールでの敬称は「どの」に統一されてました。山田どの。いま振り返るといつの時代やねん、と違和感満載ですが、当時は、先輩にそのように教えられて、違和感なく、社内メールはすべて「どの」を使っており、それが普通でした。それが、あるタイミングで「さん」に変わり、統一されました。アメリカ人や中国人でも〇〇san,と「さん」が付いてました。「どの」は変ですが、役職やMr、Mrsなどに比べて、「さん」統一は気を使わなくて楽ですよね。取引先や営業からのメールだと丁寧に会社名、組織名、役職+名前+様のように、堅苦しく、書くのも大変そうなメールも多く見受けられました。「呼称問題」は、社会人時代を思い出しながら読みました。
PART3.相田誠キャンセル騒動では、この騒動の一連の流れが語られてます。私は全く知見が無かったので、初めてこの騒動の内容、相田誠の作品絵画などを本書で知りました。実際に、Web検索で騒動になった絵画を見てみましたが、たしかに炎上しそうな作品という印象です。本文である「許される芸術」と「許されない芸術」はどこで線引きするか?考えさせられました。
普段、こういったことを考える機会が無かったので、良い機会になりました。世界一周旅行では、美術館や歴史観も訪れたいと思ってます。が、残念ながら美術のセンスも教養も無かったので、最近はyoutubeで”山田五郎 オトナの教養講座”観て勉強してます。
PART4.評判格差社会のステイタスゲームでは、ステイタスが低いと死んでしまう=寿命が短い事実のお話です。イギリスではステータスが高い=管理職の寿命が長く、もっとも低い「その他」に比べて死亡率に4倍の開きがある。面白いのは、日本では中間管理職の死亡率がもっとも高い。これ、分かるわー。と、思って読んでました。上にも下にも気を使う必要がある日本の中間管理職。日本では近年管理職になりたがらない若手が増えているそうです。みんな死にたくないので賢明だと思います。
PART5.社会正義の奇妙な理論は、リベラルな大学ほどキャンセルの嵐が吹き荒れる点やリベラルな白人による無意識の人種差別などが紹介されており、PART6.「大衆の狂気」を生き延びるは、世界でもっとも著名な作家ハリーポッターのJ・Kローリングの炎上キャンセルエピソードが紹介されています。
このパートではトランスジェンダー問題について詳細に説明されているのですが、トランスジェンダーと一括りにしてますが、実際には、トランスジェンダーの中にも種類が多くある(性転換して体もトランスする/しない等々)。そして、各々のトランスジェンダーで抱えている課題が異なる難しさなどが記されています。
正直、種類が多すぎて、理解するのが非常に難しいですが、今まではトランスジェンダーに多くの種類がある事実も知らなければ、それによって異なる課題があることも知りませんでした。何気なくニュースで聞き流していたトランスジェンダー問題について、今後はより関心が持てると思います。
このように橘玲さんの著書は、事実データに基づき(巻末に引用先が紹介)、様々な研究結果や論文、意見や事件などが紹介されており、読むことによって知見の広がりが感じれます。